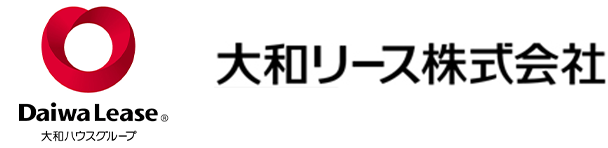更新日:2023.2.13
今回は介護業界で介護ロボットやICT化が求められる理由や国の方針、具体的な導入事例について紹介いたします。
■介護ロボットの役割と定義
・移乗支援
・移動支援
・排泄支援
・見守り/コミュニケーション
・入浴支援
・介護業務支援
■どうして介護現場にロボットが必要か
・人材不足
・介護者の負担が大きい
・被介護者の自立を促す
■国の方針
■ICT補助金とは?
・ICT導入支援事業の拡充
◇補助対象
◇補助要件
◇補助上限額等
◇補助割合
◇補助割合を拡充する要件
・都道府県別の現在の対応状況
■まとめ
介護ロボットの役割と定義
ロボットの定義は以下の3つの技術を有した機械システムを指します。
- 感知(センサー系)
- 判断(知能・制御系)
- 動作(駆動系)
介護ロボットとは上記の技術を応用し、介護分野に特化した役割を担うロボットと定義できるでしょう。なお、経済産業省と厚生労働省における「ロボット介護機器の開発重点分野の改訂(平成29年10月)」では、介護ロボットに対する6つの開発分野において支援が実施されており、今後ますます介護現場での支援が想定されています。
・移乗支援
装着型機器を用いての介助者へのパワーアシスト、あるいは非装着型機器を利用し、抱え上げ動作のパワーアシストを実施します。
〔関連商品〕マッスルスーツエブリィ
・移動支援
屋外での被介護者への外出サポート、屋内での移動や立ち座りのサポートを実施。さらに装着型の移動支援機器によ る歩行・転倒サポートも期待されます。
・排泄支援
ロボット技術を用いた排泄物処理、トイレ誘導、そして下着の着脱などにおける一連の動作支援を実施します。
・見守り/コミュニケーション
プラットフォーム機器による、施設あるいは在宅での見守りを実施します。生活支援機器による被介護者とのコミュニケーションも期待されます。
〔関連商品〕メンタルコミットロボット PARO(パロ)
〔関連商品〕シルエット見守りセンサ
・入浴支援
ロボット技術を用いた、入浴支援を実施します。
・介護業務支援
上記5分野の介護業務に伴う情報を収集し、それを基によりニーズに合う介護を行えるようにします。
どうして介護現場にロボットが必要か
介護ロボットに対する期待の高まりは、日本社会における現状や介護現場における問題などが背景にあります。介護現場にロボットやICT化が求められる理由として、以下の3点が主なものとなっています。
・人材不足
日本の総人口は今後減少に転じていくと予想されている一方で、介護ニーズの高い高齢者の割合も高くなって行くと予想されています。そのような介護の現場における人材不足に対応すべく国は「外国人・中高年人材の活躍推進」「介護現場における更なる処遇改善」などと並んで「介護ロボットの活用」を対策の大きな柱としています。
・介護者の負担が大きい
「職場における腰痛予防対策指針」(厚生労働省)でも福祉・医療分野等における介護・看護作業者には腰痛発生が多いとし、予防対策を示しています。それほどに人の手による移乗・移動支援などは、介護者の身体にも大きな負担がかかります。
そのため介護者の腰痛の発生・腰への負担を軽減し、介護者をアシストするロボットの実用化が期待されています。
・被介護者の自立を促す
ICT(情報通信技術)の活用により被介護者の見守り負担軽減も期待できます。 被介護者の中には、介護者に対する恥ずかしさや申し訳なさを感じているケースも少なくないようです。介護現場におけるロボット技術の普及は、このような介護される側の心理的な負担軽減にもつながることが期待されます。
〔関連商品〕足が不自由でも自分でこげる足こぎ車椅子コギー
国の方針
介護ロボットについての政策は、厚生労働省と経済産業省による平成24年度の「ロボット技術の介護利用における重点分野」の策定が出発点となっています。ここに示されるように両省庁が連携し、介護ロボット開発における支援を明確にしています。平成25年度と平成29年度には改訂版が発表され、支援を行う分野を当初の4分野5項目から、5分野8項目へ。最終的に6分野13項目へと大幅に拡大しました。また、平成28年には「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定されました。ここでは介護人材確保において、介護ロボットの活用を促進すると明記されています。
ICT補助金とは?
ICTとはInformation and Communication Technologyの略であり、日本語では「情報通信技術」と訳されます。
現在、ICT化は様々な分野で進められていますが、介護現場においても同様です。ICTを導入することにより、従来の紙媒体でのやり取りよりも情報共有がスムーズになったり、行政へ提出する文書作成が容易になったりと、業務効率化による介護サービス事業職員の負担軽減が見込まれています。
とはいえICT化を進めるためには、必要なタブレット端末やソフトウェアの購入などが不可欠となり、かなりの費用がかかります。
ICT補助金は、そのようなICTの導入費用の一部を助成するための補助金です。
ICT導入支援事業の拡充
ICT導入支援事業の実施自治体数は年々増加しており、令和3年度においては全ての都道府県において実施されています。
また、令和元年には195事業所に留まっていた助成事業所数も、令和3年には5,371事業所までに大幅に増加しています。
(出典:「介護分野におけるICTの活用について」(厚生労働省))
また、厚生労働省の「令和5年度 予算案の主要事項」より、「ICT導入支援事業(地域医療介護総合確保基金(介護従事者確保分)」の拡充内容が発信されました。
それにより、補助対象や補助割合要件が下記の赤字部分の通り拡充されます。
◇補助対象
・介護ソフト
記録、情報共有、請求業務で転記が不要であるもの、ケアプラン連携標準仕様、入退院時情報標準仕様、看護情報標準仕様を実装しているもの(標準仕様の対象サービス種別の場合。各仕様への対応に伴うアップデートも含む)、財務諸表のCSV出力機能を有するもの(機能実装のためのアップデートも含む)。
・情報端末
タブレット端末、スマートフォン端末、インカム等
・通信環境機器等
Wi-Fiルーター等
・その他
運用経費(クラウド利用料、サポート費、研修費、他事業所からの照会対応経費、バックオフィスソフト(勤怠管理、シフト管理等) 等
◇補助要件
・導入計画の作成、導入効果報告(2年間)
・IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「ひとつ星」または「二つ星」いずれかを宣言
・以下に積極的に協力すること 等
ICTの活用により収支状況の改善が図られた場合においては、職員の賃金に還元すること(導入効果報告により確認)
LIFEによる情報収集・フィードバック
他事業所からの照会に対応すること
◇補助上限額等
職員数に応じて都道府県が設定
| 1~10人 | 100万円 |
| 11~20人 | 160万円 |
| 21~30人 | 200万円 |
| 31人~ | 260万円 |
◇補助割合
一定の要件を満たす場合は、3/4を下限に都道府県の裁量により決定
それ以外の場合は、1/2を下限に都道府県の裁量により決定
◇補助割合を拡充する要件
3/4に拡充(以下のいずれかの要件を満たすこと)
・ケアプランデータ連携システム等の利用
・LIFEの「CSV連携仕様」を実装した介護ソフトで実際にデータ登録を実施等
・ICT導入計画で文書量を半減
(出典:令和5年度 予算案の主要事項(厚生労働省))
これらの拡充により、介護現場における更なるICT化が期待されます。
都道府県別の現在の対応状況
2023年1月現在は、どの都道府県でも令和5年度の受付は開始されていません。
今後、各都道府県ごとに開始されていくかと思われますが、対象要件や申請期間なども各都道府県により詳細な情報が異なります。そのため、最新情報や詳細については、各都道府県にてご確認ください。
まとめ